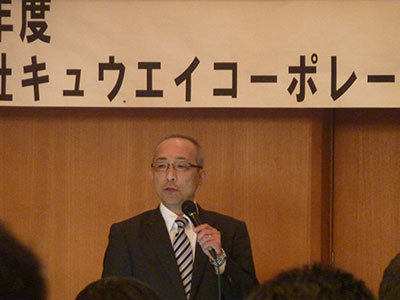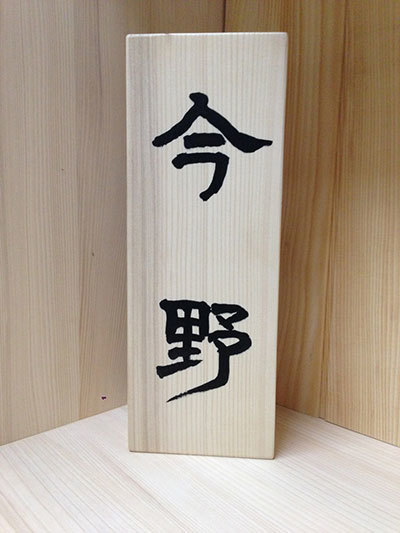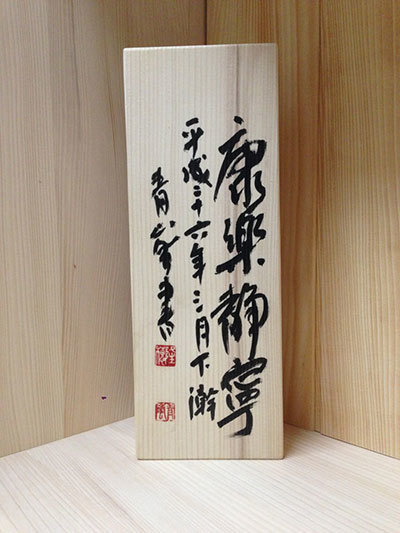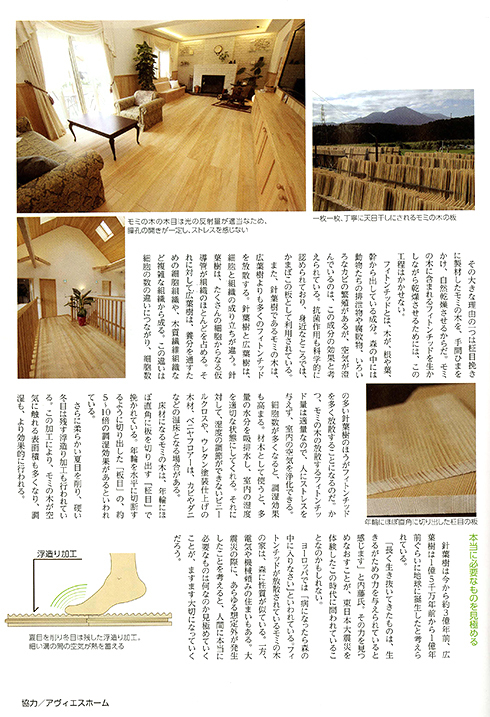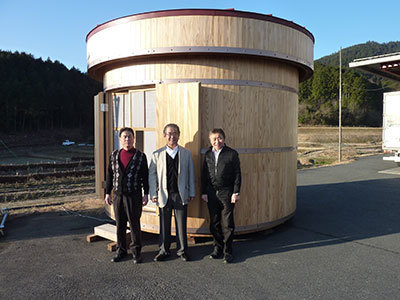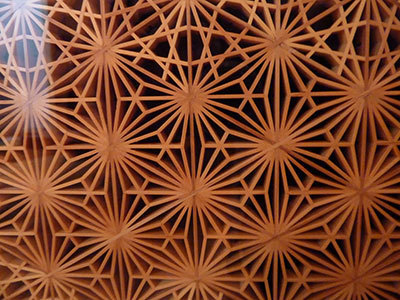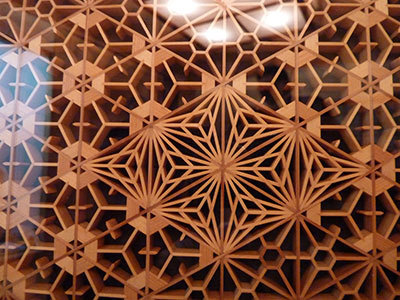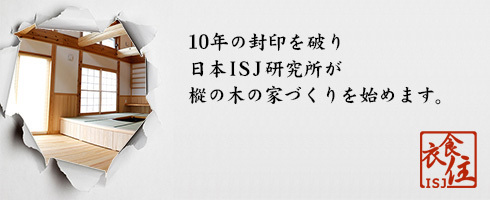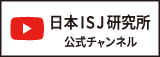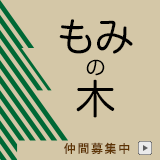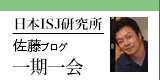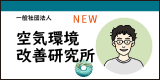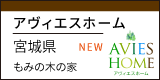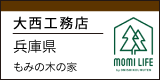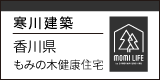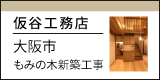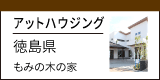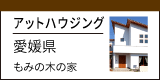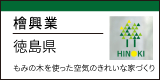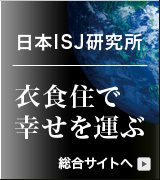歩いた道が自分の道
山住神社をお詣りした帰り道、眺望の素晴らしいスーパー林道を通って行くつもりでしたが、まだ通行止めのため元来た道で帰ることにしました。

途中、吊り橋があったので車を止めて歩いてみようかなと思い、みんなを誘いましたが、行く人、やめる人、歩いてみたけど怖がって帰る人、いろいろでした。でも新人の女性たちはサスガに素晴らしい。

これからのキュウエイを支えていくのは女性たちかもね。
行く前に答えを出すよりも行かなければ答えなんてわからないよね。
歩いた道が自分の道
なんだからね。