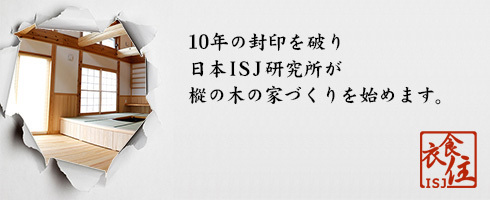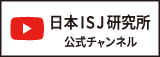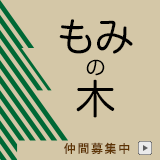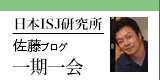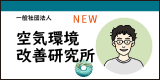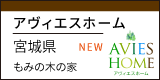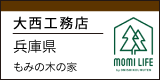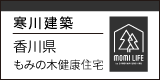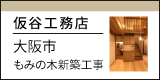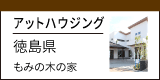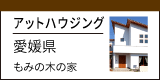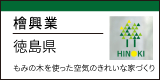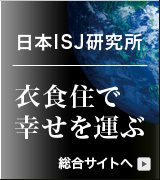衣食住で幸せを運ぶ 日本ISJ研究所
使って納得!見て納得!鹿児島&宮崎/もみの木ツアー
もみの木ツアー、
それは、内藤社長に誘われて二つ返事で、とんとん拍子に話が進みました。
思い返せば3年前、内藤社長にリフォームしてもらった廊下!それが私と‘もみの木’の出会いでした。この感触・・・何かが違う・・そんな第一印象でした。そして、いつしか子供達も廊下で遊ぶ様になり、何でいつも廊下で遊ぶの?と聞くと、だって気持ちいいんだも〜ん・・・正直な答えでした!

そもそも、母屋のベニアフロアの廊下が腐りかけ、歩くとべこべこする状態で、合わせて100歳になる祖父の介護もあり、車椅子で廊下を行き来する必要もあり、リフォームする事になりました。その時、内藤社長から紹介されたのが‘もみの木のフローリング’でした。内藤さんが言うなら間違いないと思い、すべておまかせしました。
その答えが、先程の子供達の感想だと思います。
たまたま、我が家は廊下の横に洋間があり、一般的なウレタン塗装のフローリングでした。冬は冷たく、靴下なしでは居られない。夏場は、逆にべとべとして、とても、くつろぐには程遠い状態でした。同じフローリングでも、こんなに違うのか?・・・衝撃的でした!正直な感想です。
その後、離れを新築する事になり子供達に、いろいろな材料を見せて床は何がいい?と聞くと3人とも、‘もみ’!!子供は正直ですね〜。もちろん、自分も嫁さんも同じ意見。家族全員一致という事でリビングはもみのフローリングにしてもらいました。子供たちには、それぞれ部屋も作ったのですが食事も勉強も寝るのも殆どリビングです。他の部屋を使わないのは少々もったいない気はしますが、逆に気持ちいい空間で家族が一緒に過ごせる・・・これって大切ですよね。

今では、どんなに遅くなっても家に帰りたい!1時間でも2時間でももみの床でゴロ〜ンとなりたい!なぜか疲れがとれるんです。そんな、ユーザー目線でもう一度もみの加工現場を見せてもらおうと、行く前からとても楽しみでした。
つづく
製材工場でモミづくし
昼食を挟み、今度はもみの木の製材を行っている加工場へ。

前回と入り口付近が違うと思ったら、敷地を拡張されショールームが出来ておりました。
そのショールームで社長自らコーヒーを入れていただき、いろいろと見せていただきました。中に入ってビックリ!、和風かと思いきや和のテイストの中に洋もあり、そして遊び心も取り入れたすばらしい空間でした。



まず目に飛び込んできたのが、もみの木のフローリングをデザイン畳の様な貼り方にしてある点でした。照明・引き戸・テーブル・・・あらゆる物にデザイン性を感じ、同じ材料を使ってもデザインをプラスすることで他とは違うワンランク上の提案が出来るのではないかと思います。非常に見る価値のあるショールームでした。材木屋さんとは思えぬ社長の風貌とセンスに脱帽です!

そして、いよいよ工場内へ・・・周りには前回同様、巨大なもみの木の丸太がゴロゴロと・・・この大きさ、数には圧倒されます。最初の皮むきも、機械に掛けれない物はハンディーの皮むき機でむいておりました。とても労力がかかります。自分も家のお茶の葉を、茶刈り機で刈りますが、重くてすぐに腕が痛くなって大変です。それを黙々とやられている姿には尊敬しました。

次に製材している現場を見せて頂きました。すべて柾目で丁寧に製材されており、その後、1枚1枚グレード別に仕分けをされておりました。これも目利きのいる作業です。これらの中で一番グレードの良い物がもみの木の床材になるそうです。思わず見入ってしまいました。

そして天然乾燥の作業場へ。1枚1枚干していく・・・気の遠くなる作業と量です。人口乾燥機ならリフトでパレット毎、乾燥室へ入れると思うのですが、ここの作業は違います。あえて、この乾燥方法を貫いているとの事・・・頭が下がります。柾目引き・天然乾燥・浮づくり加工・・・これらが、本来の木の成分・特性を生かすという事なのでしょうね。納得・納得!
話は違いますが、静岡県の由比漁港近辺で行われている桜えびの干し場を思い浮かべました。桜えびも天日干しする事で、身も締まりおいしさも増すとの事です。きっと、もみの木も自然の恵みを受けて丁度よい成分になるんでしようね〜。改めて納得しました。

製品工場内では、神社のお札、結納台、絵馬の材料など所狭しと加工されておりました。今の時代、神事や結納事など、かなり減っているのかなぁ〜と思いましたが、この工場内を見る限りまだまだ需要はあるんだと感じました。それは、やはり昔からの製法にこだわり、丹精込めて人の手で作り上げる・・・これが海外で作るのとは違い、使う人にも訴える事が出来るのではないでしょうか?

社長が、今度出来たショールームで、全従業員と語らう時間を持つとおっしゃっていました。まさしく、社長の気持ちが従業員に伝わり、それが良い製品を作る・・・社長の姿勢に頭が下がります。次回おじゃまする時は、自分も参加させて下さい。(1日目は、天文館・・・2日目は社長のショールーム!!)
酒蔵の壁に張られたもみの木

酒蔵に入った時のとてもいい香り・・・酵母が生きているという表現がピッタリです。もみの木の壁、貯蔵樽・・・その空間がとても絵になります。前回も運よく見せて頂きましたが、今回は杜師でもある御主人のお話をいろいろ聞く事ができました。酒づくりも大変奥が深く、その時期に採れた芋の具合、麹菌の具合、そして発行の具合・・・どれひとつ欠けてもおいしい酒は出来ないとの事。
一時期、理想の味が出せなくて随分苦労された様ですが、その努力の末のとてもよい表情をされておりました。堂園さんが同伴しないと見せてくれないのも納得できます。堂園さんも後程、書かせて頂きますが、お客様の為には何がベストか?常にお客様目線で物造りをされている方です。自分はとても及びませんが映像の作り手としてお客様にとって何がベストなのか、いつも自問自答しております。
尾込商店の御主人、堂園さん・・・相通じるものがあります。この人たちと出会えた事に感謝し、その考え方を直接聞けて、今後の自分にとって、とてもプラスになりました。
ありがとうございました。
現代の100年住宅
◇堂園さんの建築現場
焼酎の香りを惜しみつつ堂園さんの建築現場へ・・・ここは、まさしく堂園ワールド!高床式の平屋・・・まさしく南国鹿児島ではベストな造りではないでしょうか?


自分が住宅でいつも気になるのは床下の湿気です。でもこの工法なら大丈夫だと思います。あと、昔ながらのほぞを作り、材と材を合わせていく・・・現代ではこの様な手間をかける事は殆どしないと思います。でも、自分の嫁の実家、築100年程の家は確かにこの様な造りをしています。この堂園さんの建て方が、まさしく現代の100年住宅ではないでしょうか?



外壁も板で囲い、そこには天然のニスを塗る・・・実によいバランスです。建てる時は20代・30代かもしれませんが、自分が60代、70代になった時を考えて下さい。やはり、和風が落ち着くんではないでしょうか?まさしくそれを象徴する家造りだと思います。

何より堂園さんの人柄に惚れてしまいます!!ありがとうございました。
樅の木を大好きになって良かった
※終わりに・・・
楽しみにしていた2日間はあっという間に過ぎてしまいました。帰路の飛行機の窓からは、久々に大きく噴火した桜島が見えました。この桜島のエネルギーの如く、このもみの木パワーを必要としている人へ、ユーザー目線で伝いたい・・・そんな思いで一杯になりました。
おって、このツアーのDVDも作ろうと思っております。今しばらくお待ち下さい・・・
最後に、この様な機会を作って頂いた、日本ISJ研究所の内藤社長、誠にありがとうございました。
本音で語る家づくり
家づくりの基礎 木材辞典
サービス案内
- もみカフェで会いましょう